10月2日(日)のTBSの番組「噂の!東京マガジン」で、見出し大賞となった「週刊実話」の記事は、地球温暖化とミニ氷河期到来についてのものだった。
価格.com – 「噂の!東京マガジン」2016年10月2日(日)放送内容 | テレビ紹介情報
週刊実話
今週の見出し大賞は週刊実話。地球温暖化を覆すミニ氷河期到来で専門家が真っ二つ。南極では氷が増え、97%の確率でミニ氷河期の到来を訴えている人も。一方気候変動専門家は真っ向対立。
エンタメ系(というよりエロ系)の週刊誌の中の、小さな記事なので、内容的にはさほど詳しくはない。地味な記事だし、表紙の見出しに出ていない記事でもある。
この記事が選ばれたのは、選者の興味と「温暖化」というキーワードだったのだと思う。
内容は、前出の引用のとおりで、「地球温暖化派 vs. 温暖化懐疑派」の真逆の未来像についてだ。
▼週刊実話(2016年10月13日号)より
こうした異常気象は世界的な規模で起きているが、その原因は「温暖化」にあると信じられてきた。ところが、その一方で「寒冷化」にあるとした理論が台頭し、専門家の意見は真っ二つに割れている。
「地球温暖化を覆す新説が天文学者らから相次いで発表されているのです。衝撃的だったのは、昨年11月にNASA(米航空宇宙局)が発表した『西南極では従来の研究通り氷床が解けているが、東部や内陸部では逆に増加し、2002年から’08年にかけて全体では年間820億トンの氷が増えた』という説です。同説は従来からの地球温暖化による海面上昇説を覆しました」(サイエンスライター)実はロシア人科学者らは「地球は寒冷化に突入する」と主張をする人が多数派を占めている。モスクワ国立大学の美人物理学者ヘレン・ポポワ博士がその代表で、その結論を要約すると「97%の確率でミニ氷河期がやってくる」というもの。天文学と応用数学を専門とする英国の大学教授も、ポポワ博士とほぼ同じ説を唱えている。両者の根拠は「太陽の黒点が減少し、2030年頃に活動自体が現在と比べ60%低下することで、地球の気温も低下する」というものだ。
記事としては、ページの半分にも満たない短い記事だ。
私のブログの過去記事でも何度か取り上げている話題だが、地球の歴史上、温暖化と寒冷化を繰り返していて、その時間的スケールは、数千年~数万年である。化石や地層などの間接的な痕跡から、大昔の気候を「推測」しているわけだが、実際に気温を計測したわけではないので、かなりアバウトな数字だ。
昨今の温暖化問題は、近代的な気象観測が行われるようになってからの、たかだか数十年の変化を元に未来を予想しているにすぎない。計測機器を使った観測は1860年頃からなので、19世紀までを含めても150年である。しかし、ここで注意が必要なのは、現在は世界中に気象観測網があるが、19世紀~20世紀初頭は限定的だったことだ。
京都議定書での基準年は1990年となっているが、比較対象としてよく出てくるのは20世紀半ばということで、1950年頃からの変化で、何℃上昇したかと表現される。
世界の平均気温というのも、けっこう乱暴な指標だ。
観測点をどこに置くか、どれだけ多くの観測点を置くかで、平均値は変わる。おもに人が住む地上に観測点が設置されるが、海の上にはない。都市部に観測点が置かれていると、都市の出す熱で気温は高めになる。郊外に行けば気温は下がる。観測点が偏っているのを問題にすることは、ほとんどないのが不思議。条件の異なる観測地を足して平均を出すことに、どれほどの意味があるかは疑問。
インドで50℃を超えたというニュースがあったが、同じ日同じ時刻の南極ではマイナス50℃だ。極端な例だが、両方を足して割ったら、平均気温が0℃というのにはあまり意味がない。
地球環境は、全体でバランスを取る。大気は循環し、水も循環する。干ばつになるところがある一方で、洪水になるところもある。地球上に存在する「水」の総量は基本的に変わらないので、その水がどこに偏在しているかだ。
関連して、以下の記事。
結局、本当に「地球温暖化」って起きているんですか?(熊谷 達也) | 現代ビジネス | 講談社
いや、温暖化などという生易しいものではなく、気候は暴走に向かおうとしている。そう警告を発しているのが『気候の暴走』だ。読み始めてすぐ、本書で紹介されている未来予測に、めまいがしそうになった。熱波や干ばつ、台風の巨大化や洪水といった気象災害の頻発はもちろんのこと、水や食料の不足、感染症の蔓延、海面と海水温の上昇、海洋の酸性化等々、挙げていけばきりがない。
(中略)
手にしたのが『地球はもう温暖化していない』であった。
タイトル通り、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書が依拠している気候モデルへの疑問―現実の観測結果が気候モデルの予測から乖離している等―を示した上で、CO2が温室効果を持つのは事実であるものの、人為的CO2排出が温暖化の直接的な原因ではなく、そもそもCO2と気候変動は関係がない、と述べている。では、何が気候変動をもたらすのか。その主役は、CO2ではなく太陽活動だというのだ。
本書によれば、太陽の磁場が地球に届く宇宙線の量を決定し、それが地球上の雲の発生量を左右して気候変動をもたらすとのこと。そして現在、太陽活動は弱まる傾向にあり、結果的に雲の量が増え、今後の地球は、むしろ寒冷化する恐れがあるらしい。
ここに出てくる寒冷化説が、「週刊実話」のミニ氷河期到来説につながっている。
IPCCの気候予測モデルで、太陽活動を考慮に入れないというのも疑問だ。地球が生命の宿る暖かい惑星なのは、太陽のお陰だ。太陽なくして地球に生命は誕生しなかった。地球が太陽を公転して1周するのを1年としているが、その軌道は毎年同じではなく、少しずつ変化している。太陽系自体も、銀河系の中を公転していて、去年と今年では宇宙の中での地球の位置と環境は変わっている。
毎年毎年、カレンダーは循環しているように感じるが、実際には毎年毎年違う環境に地球は置かれている。太陽活動が地球の気候に影響するだけでなく、銀河の中に存在するダークマターも地球の気候に影響するとの説もある。それらの影響力は低いかもしれないが、ゼロではない。ある気候変動を起こす引き金になっているかもしれない。しかし、その実態は不明だ。
わずかな変化が大きな変化に発展することを、バタフライ効果というが、気候というカオスな現象では無視できない要素のはずだ。
過去の気象において小氷期などが、太陽活動の変化と関連していることはほぼ定説になっている。にもかかわらず、現在の温暖化論議で太陽活動を無視するのはどういうわけなのか?
もはや既定路線となっている地球温暖化だが、旗振り役のIPCCは政治的に振る舞っているので、いささか胡散臭く感じてしまう。
温暖化のメカニズムとされている論法は、考古学的過去の温暖化を説明できていない。
縄文時代は、現在よりも温暖な気候で、海面は現在より数メートル高かったことがわかっている。その当時の関東の海岸線を示したのが以下の図。
▼縄文時代の関東の海岸線
関東平野の縄文の海-古鬼怒湾
関東平野のかなりの部分が水没している。この時代、なぜこれほどまで温暖化していたのか、明確なことはわかっていない。人間活動由来の二酸化炭素が原因でないことだけは確か。人間が関与しなくても温暖化は起きるし、逆の寒冷化も起きる。
縄文時代の前期、約6千年~5千年前に、温暖化が進行し、海水面は4~5メートル高くなった(縄文海進)。この千年間の気候変動の詳しいことはわかっていない。現在の観測のように、1年刻みでの詳細なデータは、化石や地層からは読み取れないからだ。千年の間に変化があったことはわかるが、実際には数百年だったかもしれないし、上がったり下がったりを繰り返して、結果的に千年間で温暖化したとみるのが妥当だろう。
前にも引用した文面ではあるが、再掲。
けら研,かつて人類が縄文時代に経験した急激な温暖化 松本秀明,地球の温暖化に関する情報
現在,二酸化炭素等の排出による地球大気温の上昇,そして海水の熱膨張,氷床の融解などによる海面の上昇が危惧され,全地球的な環境問題となっています。IPCC(1996)は,100年後までに海面は13~94cm上昇すると予測しています。ここから算出される年間1.3~9.4mmの海面上昇速度をどう評価するかの議論は他に譲るとして,これまで人類(新人)が経験した地球規模の海面上昇のうち,縄文時代早期のある期間に相当する今から9千年前~7千年前には,この数値を遙かに上回る年間17mmの海面上昇を記録したことが地理学の研究成果から示されます。
こうした説もあることを考えると、近代文明活動に由来する二酸化炭素排出による温暖化の進行は、自然界の温暖化プロセスには及ばないともいえる。
温暖化が進行しているとしても、その主役は人間が排出する二酸化炭素ではなく、本当の主役は自然界が起こしているのかもしれない。たまたま、その時期が「今」だった……ということだってありえる。
じつのところ、温暖化に関わるガスとしては、二酸化炭素よりメタンガスの方が影響は上であり、さらに水蒸気の方が上回る。諸説あるが、水蒸気の温室効果寄与率は、65%から最大95%になるという。温暖化を危惧するのなら、減らすべきは二酸化炭素ではなく水蒸気なのだ。
寒い冬の時期、快晴の朝は放射冷却で気温はかなり下がる。しかし、雲が空を覆っていると地表の熱が空に逃げずに残り、暖かい朝になる。二酸化炭素にここまでの温室効果はない。
二酸化炭素が増えた、増えたといいつつも、その濃度はppmで測るようなごく微量であり、目の粗いザルのようなもの。密度の濃い毛布のように地球を覆っているわけではないし、二酸化炭素が吸収する赤外線の波長は一部なので、熱の大部分は宇宙に逃げられる。
温室効果ガス世界資料センター (WDCGG)の解析による2014年の世界の平均濃度は、前年と比べて1.9ppm増えて397.7ppmとなっています。
この397.7ppmというのが、どのくらいの濃度なのかがわかりにくい。
ppmとは、パーツ・パー・ミリオンの略で、100万分のいくらかを表す。1ppmは0.0001%で、397.7ppmは0.03977%ということになる。
25メートルプール(長さ25m、幅16m、水深1.5mと仮定)にたとえると、水の量は約540トン。その0.03977%は、約215kg。体重50〜60kgの人が約4〜5人分。5人がプールに散らばり、熱に見立てたピンポン玉を天井から一斉に落として、何個キャッチできるだろうか? キャッチするための「たらい」や網を持っていてもいい。……というイメージを浮かべて欲しい。
ピンポン玉の直径は40mmなので、25mプールの面積では、25万個が一斉に降ってくることになる。
大部分はスルーだ。
397.7ppmの網目では粗すぎて、一部の熱しか捉えられず、温室としては役に立たない。
……と、以上は、397.7ppmがどの程度の密度なのかの思考実験であり、温暖化を単純化したイメージではないので勘違いしないように。
大気層は地表から500kmに及んでいるので、温室効果ガスはその間に分布している。薄い膜を連想するが、実際にはスポンジのように層状に温室効果ガスがあると考えるといいだろう。
目の粗い二酸化炭素の網が、何層にも重なって下層で取り逃がした赤外線を上層で吸収する。しかし、際限なく吸収するわけではなく、吸収できる限界というのがある。
これについて、よい記事があった。
つまり、285ppmの二酸化炭素のもつ赤外線吸収能力17%のうち実効的に働いているのはメタンと酸化窒素の影響を考慮しても、高々17-(14-1.2-0.5)=4.7%に過ぎないということになります。つまり、波長15μmの帯域においても、水蒸気による吸収の方が圧倒的に大きいのです。
(中略)
仮に次の標高100~200mの大気が同じ比率で地表面からの赤外線を吸収するとすれば、94+(100‐94)×0.94=99.64%≒100%を吸収してしまうことになります。このように、工業化以前の二酸化炭素濃度であったとしても、温室効果に有効に働く二酸化炭素濃度は既に十分であったと考えられるのです。
Jack Barrettのレポートから、工業化以前の大気においてさえ既に温室効果に有効に働く大気中二酸化炭素濃度は飽和していると見なしてよく、近年の大気中の二酸化炭素濃度の上昇で気温が顕著に上昇する可能性はほとんど考えられないのではないかと思われます。
下線は私が引いた。なかなか説得力のある分析だと思う。
また、出典が不明確ながら、以下のような記述もある。
地球は二酸化炭素の排出などによる温室効果で温暖化していないと思って… – Yahoo!知恵袋
1865年に炭酸ガスが温室効果ガスであることを発見したチンダルはその後の実験で炭酸ガス濃度を2倍にしても炭酸ガスによる吸収が増えないことを明らかにしました。
この投稿をした人は、あちこちのQ&Aサイトで同じことを書いているのだけど、出典または原典がわからない。チンダルは「チンダル現象」で知られる、ジョン・ティンダル(John Tyndall)のことだが、炭酸ガスやメタンガスに温室効果があることを発見した、という記述はあっても、「濃度を2倍にしても炭酸ガスによる吸収が増えない」という実験について触れている記事がほかに見当たらない。
19世紀の実験なので、現代において追試した人はいないのだろうか?
これ、けっこう重要なことだと思う。濃度が倍になっても温室効果に変化はないとすれば、二酸化炭素削減のためのパリ協定なんて、無意味な茶番になってしまう。
パリ協定は環境問題を第一に考えているというより、政治的・経済的な側面が強いように思う。
これまで途上国が温暖化問題には消極的だったが、パリ協定では賛同した。二酸化炭素の排出規制は、先進国にとっても経済の足かせになるが、発展めざましい途上国にはより強い足かせになる。経済成長が鈍っている先進国は、自分たちの足を縛ってもなお、途上国の足を縛る方が得策だと判断しているのではないか?
世界のトレンドの主導権を、先進国が握り続けるための「餌」というか「脅威」として、地球温暖化問題を利用しているように見える。
また、「二酸化炭素による温室効果は飽和している」という論考が以下にある。かなり専門的で読みにくいが、なかなか興味深い。
温室効果飽和に対する愚かな反論 | RealCrazyClimate
第1章で解説したとおり、CO2の温室効果が飽和することは厳然たる科学的事実であり、事実を否定できるはずがない。
結局のところ、IPCC学派は、飽和しないから飽和しないのだと、非科学的極まる論理を振りかざしているにすぎない。問題は、未だ飽和状態から遠いのか否か、ということであるが、第3章で解説したとおり、「吸収、放出がくりかえされる回数」は80に達しており、従って、(2-4)式から判るとおり、15μm帯域の温室効果は既に7℃に達しており、そして、(1-15)式で導いたとおり、上限は8℃だから、15μm帯域の温室効果が上がる余地は1℃しか残っていない。
しかも、次章で解説するとおり、実は、0.5℃しか残っていない。
CO2の温室効果は既にほぼ飽和しているのだ。
とまぁ、温暖化の肯定派と懐疑派は、それぞれの主張をしている。
どちらが正しいのかは、早ければ15~50年後、遅くとも100年後には、そのときの気候がどうなっているかで判明する。
そもそも人間の活動自体も、地球環境の中では変動要素のひとつにすぎない。大規模な火山噴火が起これば、ほんの数日で莫大な量の塵やガス(二酸化炭素を含む)を放出する。それは化石燃料を燃やすことで出てくる二酸化炭素など、屁でもない桁違いな量だ。二酸化炭素よりも塵の方が気候に対する影響は大きい。
アメリカのイエローストーンの地下には、巨大なマグマ溜まりがあり、将来、大爆発をすると予想されている。それが起これば、アメリカは壊滅的になるし、地球環境は激変する。人間が起こせる環境変化など微々たるものなのだ。
私は地球温暖化懐疑派というわけではない。
温暖化を説明する理論には、穴があり、完璧ではないことを疑問視している。それはあくまで仮説のひとつであり、寒冷化説と同等くらいの可能性を示しているにすぎない。
仮に温暖化が予想通りに進行したとしても、なにも心配する必要はない。海面が4~5メートル高くなるほど温暖化していた縄文時代でも、生物は絶滅するどころか繁栄していた。急激な変化で絶滅する種もあるだろうが、それ以上に繁栄する種が登場する。生態系が変わるだけなのだ。
ただ、その変化には数百年~数千年の時間はかかる。しかし、地球の46億年の時間スケールでいえば、数千年はほんの一瞬だ。
そして、何度も書いている結論は……
たとえ、第6の大量絶滅が起こったとしても、進化の歴史を1からやり直す時間は残されている。太陽の寿命は約100億年と推定されているが、まだ46億年が過ぎただけ。人類につながる祖先が恐竜の足元で齧歯類として生きていた頃から、人類に進化するのに要した時間は約6500万年。1億年はかかっていないのだから、人類が滅びても、次なる進化で知的生命体が誕生する時間は十分にある。
心配しなくても、地球上の生命は、太陽が赤色巨星化するまで繁栄する。
そこに人類がいなくても(^_^)。
「地球46億年の歴史から考える地球温暖化」に続く



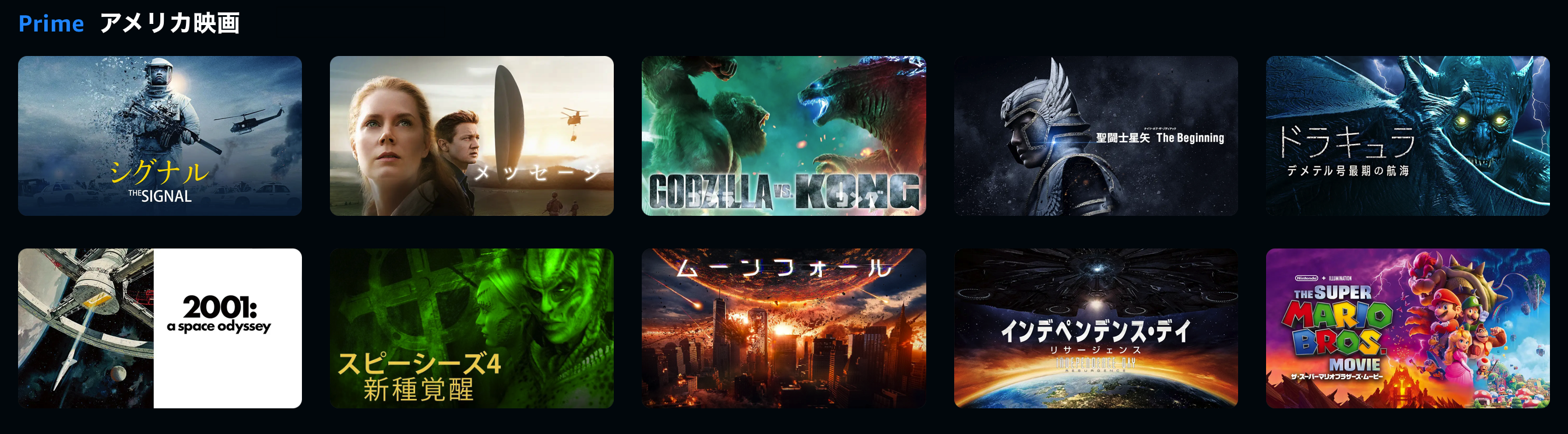
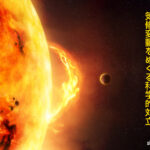





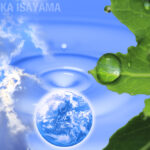



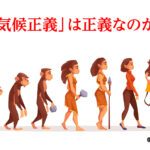



コメント