『涼宮ハルヒの消失』を、昨日の日曜に観てきた。
映画館が限られているので、今回はアバターと同じ「ユナイテッドシネマ豊洲」
本当は初日の土曜に行きたかったのだが、いい席の予約が取れず、日曜になった。いい席というのは、館内を横切る中央通路に面した、真ん中の席で、いつもそこの場所を予約して取る。
予約が開始されて数時間後には、いい席が埋まっていた。満席ということはなかったが、中央よりの席は、早々と埋まっていたようだ。
映画はTVシリーズの続編的な話になっているため、映画単体だけでは物語やキャラクターの相関関係がわからないだろう。
オープニングの曲も、TVシリーズと同じだった。アレンジは違っていたようだが。
というわけで、久々にハルヒ・ワールドに帰ったきた感覚。
以下、ネタバレありなので、ご注意を!
今回の映画では、「キョン」が主役で「ハルヒ」の出番は少なくなっていた。
もともと、キョンの独白的なセリフで世界観を表現していたのだが、「消失」ではハルヒが消失することにもなっていて、ハルヒの活躍を期待していたとしたら、ちょっと拍子抜け。
観ていて思い出したのは、『うる星やつら ビューティフル・ドリーマー』だった。
![うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー [DVD]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519XK5GV6EL._SL160_.jpg)
うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー [DVD]
まったく違う物語だが、雰囲気が似ている。
日常と非日常が交錯して、どちらがほんとうの世界なのか?
……といった、自分のいるべき世界、望む世界の葛藤が起きるあたりが、似ていると連想させる。
そして、重要なキーワードでありシチュエーションなのが、「高校生活」のイメージと存在価値だ。
『true tears』『初恋限定。』のレビューでも書いたことだが、「高校生活」が思い出となっている世代には、あの年頃、あの時代のイメージは甘く、切なく、郷愁を誘う。
キョンもまた、そういう思いを口にする。
とはいえ、現役の高校生が高校生活の3年間に、郷愁を抱くことはない。その思いは、キョン自身ではなく、作品を作っているスタッフの思いだろう。
自分が高校生だった頃を思い出してみれば、楽しいこともあったが、辛いことや悩むことの方が多かった。3年間がやけに長く感じて、いつになったらこの苦しみから解放されるのかと思っていた。早く大人になりたいと思うのは、悩みの泥沼から抜け出したかったからだ。
歳を取るほどに、時間が過ぎるのが早くなったように感じられ、3年なんてあっという間になった。
だが、高校生だったときには、1年が長く長く続いた。
いつまでも高校生から卒業できないような錯覚すらしたものだ。
それには理由がある。
17歳の高校生には、1年は17分の1の時間だ。
対して50歳の人には、1年は50分の1だということ。
時間感覚には、約3倍の違いがある。
つまり、50歳の人の感覚からすれば、高校生活は9年に相当する。30代の人であれば、2倍の6年相当だ。高校時代は、それだけ長い時間だったのだ。
過ぎてしまえばあっという間でも、そのときは終わりのない時間に感じられる。
キョンやハルヒの時間に共鳴するとき、懐かしさと同時に昔の時間感覚に戻るような気がする。
バカバカしいことに夢中になり、日常の現実と想像の非日常が入り乱れて、両者の境目が曖昧になる。それを物語として具現化したのが、ハルヒの世界だ。
非日常的なハルヒの存在が消失して、ごく当たり前の日常になったとき、キョンは違和感を感じる。
それは高校時代を卒業して、現実的な社会に適応した大人の視点だろう。それが現実的であり、リアルな世界だとわかっていても、どこか馴染めない。自分の居場所が失われてしまったような喪失感。
大人になるというのは、夢を捨てること、目の前の現実に抗うことなく対処すること。それが処世術……だとしても、どこか割り切れない。しかし、歳を取るほどに、その感覚が鈍り、簡単に割り切れるようになる。いつしか、普通の大人になってしまう。
ハルヒの世界に懐かしさや共感を感じる「大人」は、まだ割り切れない感覚を残している、大人になりきれない大人だろう。
少年の心を持った大人……といえば、聞こえはいいが、じつのところ、少年の心を引きずった大人だ。引きずっているから、ボロボロで擦り切れ、いまにも千切れてしまいそうな状態だ。だが、そのボロを役に立たないとわかっていても、捨てきれない。
映画を観ていて、ふっ……と、目が潤んでしまう。
ありえない高校生活でも、あってほしかった高校生活。
あの頃は、想像力でなんでも可能な気がした。
けっして充実した3年間ではなかったが、あの頃は、たしかに存在した。
キョンが求めたのは、その存在感だったのだろう。
それは、歳を取った私たちにも共感できる存在感だ。
キョンやハルヒは、永遠に高校生のままだ。
終わることのない高校生活。
それは「ビューティフル・ドリーマー」と同じ。
彼らは大人に目覚めてはいけない。
高校生のまま、存在し続ける。
彼らの存在が、私たちを昔の自分に回帰させてくれるからだ。
ラスト。
スタッフロールが流れ終わって、もうひとつのシーンが出てくる。
図書館で、幼い少年少女がなにやらやり取りしていて、それを長門が見つめている。
少年は少女のために、図書館カードの申請書を書いてあげているようだ。
このシーンの意図は、明確ではない。
あえてこういうシーンを入れているということは、このシチュエーションが、長門が改変したもうひとつの世界の記憶と類似しているという暗示なのか?
だとすれば、長門は改変した世界の記憶を持っている……ということなのかもしれない。
ひとつの解釈ではあるが、よくわからない。



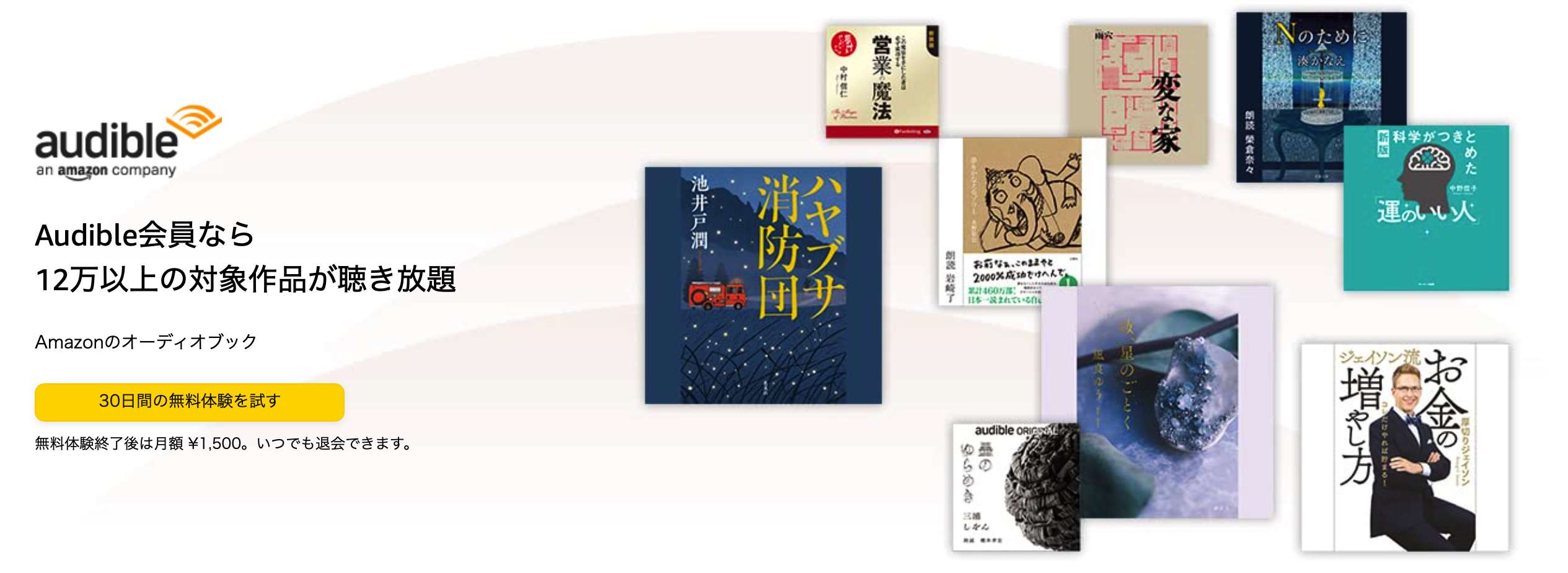














コメント